それぞれ個別には幾度か参拝したことはあるのだが、通しとなると初めての事だった。
今回のポタリングでこのルートを選んだのは、ボクの家から往復120kmほどの道程で、未だ決まらないバイクのセッティングには丁度良いかなって感じだったからだ。本当は、暗がりヒルクライムリベンジといきたかったのだが、今の状態では無理そうなので止めておく。それは、ここでは未だ書いてはいないのだが、香川でのヒルクライムで膝を痛めた不安が頭を過ぎったからだった。
またもや時系列が無茶苦茶ではあるが、その時の経験を活かしての変更点は、と云えば、"サドルを数ミリ上げる"、"左足のクリートを数ミリ下げる"の二点である。一番大切そうな尿道への圧迫は、サドルを変えないことにはどないしようもない、と云った金銭的な問題故、今回は放っておくことにした。
下之太子
 "椋樹山大聖勝軍寺と称し、高野山真言宗に属し、叡福寺(太子町)に対して、「下の太子」という。
"椋樹山大聖勝軍寺と称し、高野山真言宗に属し、叡福寺(太子町)に対して、「下の太子」という。聖徳太子は物部守屋を滅ぼすにあたり、四天王に祈願、その加護によりいくさにかったので、この寺を建てたという。
明治二十一年(一八八八)の台風で大堂(地蔵堂)が倒壊し、昭和四十六年復興が計画、旧太子殿の背後に新太子殿が建った。
本尊は如意輪観音(府重要文化財)で寺宝も多い。門前に守屋池、付近には鏑矢塚、弓代塚、市民病院前には物部守屋大連墳がある。
中之太子
 "当寺の創立は蘇我大臣といい、また聖徳太子建立四十六院の一とも称するところから、叡福寺の「上の太子」将軍寺の「下の太子」に対し「中の太子」と俗称せられている。所在地の旧郷名が野中郷であってその地名による俗名を野中寺といい『日本霊異記』には野中堂と記している。また正倉院文書によれば当郷は百濟系渡来系氏族船史のちの船連の本貫であったから、その氏寺であったことが察せられる。
"当寺の創立は蘇我大臣といい、また聖徳太子建立四十六院の一とも称するところから、叡福寺の「上の太子」将軍寺の「下の太子」に対し「中の太子」と俗称せられている。所在地の旧郷名が野中郷であってその地名による俗名を野中寺といい『日本霊異記』には野中堂と記している。また正倉院文書によれば当郷は百濟系渡来系氏族船史のちの船連の本貫であったから、その氏寺であったことが察せられる。その創立年代は境内出土屋瓦から飛鳥時代にあることが考えられる。
境域には良く旧伽藍跡の土壇および礎石配列を止めるが、対向する東の金堂と西の塔婆とを中心とするもので、その伽藍配置は野中寺式とでも称すべき特色あるものである。なかんずく塔跡の刹柱礎石は刹柱の四柱座の周囲三方に添柱のそれをも彫り加えていて当市古市の西琳寺、法隆寺創建伽藍、橿原市橘寺等のそれに類例があり、ことにその舎利納置施設として柱穴側面に横穴を穿っているのが注目される点である。
なお創建当寺の軒丸瓦には弁上に忍冬文を配した特色あるものも含まれている。
当寺の現堂宇は享保年間以降、律僧恵猛により狭山藩主北条氏を檀越として再興されたもので、その僧堂は簡素な建物ではあるが、めずらしい遺構である。
なお、僧恵恵猛は現寝屋川市太秦の秦氏の出身であって『律苑僧宝伝』『日本高僧伝』等の伝記に載録されている高僧である。"
上之太子
 "叡福寺は、推古天皇が聖徳太子のお墓を守るために建立され、のちに聖武天皇の勅願で七堂伽藍が完成されたと伝えられています。平安時代以後、聖徳太子信仰の霊場として栄えましたが、戦国時代末に織田信長の兵火にかかり焼失しました。江戸時代に豊臣秀頼によって聖霊殿が再建され、次第に整備がすすみました。毎年4月11日の太子のご命日に行われる会式は「太子まいり」と呼ばれ、多くの参詣者でにぎわいます。"
"叡福寺は、推古天皇が聖徳太子のお墓を守るために建立され、のちに聖武天皇の勅願で七堂伽藍が完成されたと伝えられています。平安時代以後、聖徳太子信仰の霊場として栄えましたが、戦国時代末に織田信長の兵火にかかり焼失しました。江戸時代に豊臣秀頼によって聖霊殿が再建され、次第に整備がすすみました。毎年4月11日の太子のご命日に行われる会式は「太子まいり」と呼ばれ、多くの参詣者でにぎわいます。"膝は痛まずサドルはOKっぽいのだが、足裏はまだ鈍く痛み出した。中敷を換えねばならないか?





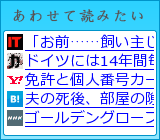
0 件のコメント:
コメントを投稿