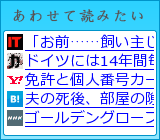山越えに継ぐ山越えと散々汗をかきまくっての日没となり、そこはそれで冷え切った身体の欲望に忠実に従って於こうと、おでんやの暖簾を潜ったのだった。カウンターには常連らしき男性がふたり。いいですか?と断りを入れ、少し離れたところに腰を据える。おでん、おでん、おでん、と、手を擦り合わせながら選んだのは牛すじ肉と厚あげに熱燗。そこは「がんも」を頼んだのだが、切れてしまった、というので厚あげへの変更であった。そこに勧められるがままに子持ちイカを追加する。


つきだしはアジの南蛮漬に青葱のぬた。地元では、わけぎ以外をぬたにするなんて有り得ないワケで、当然その仕上がりはトロッとした滑りなどなく、一口二口と食べる内は、そこに何が出されたのかも分からなかったのだが、決して不味いというほどのモノでもなかった。青葱をぬたにして供するのもこの地方独特のモノかな?なんて思いながら、ホワイトボードに書かれた「下足のしくしく」ってなんですか?と尋ねる。
「しくしく」ってのは、柔らかいって意味で、ただ単に下足焼いただけですと云う。それならそれを、なんて頼むのもなんの面白味も無いので、続けざまに本命的な「隠岐の珍味 海牛(べこ)」ってのは何かと尋ねた。それは、あの紫色の粘膜を吐き散らかすアメフラシの事だと云い、この辺り一般的に食すモノだという。今ぐらいまでが旬で、後は味が落ちるので冷凍しておくのだとか。それを甘辛く炒りつけたものがいわゆる「べこ」なのだそうだ。独特の磯臭さがあり、地元の人は懐かしがって食べるが、余所の人には勧められるようなモノではないとも云う。それでもボクは、小学生の頃から蛙の天麩羅やエスカルゴ、イナゴの佃煮なんかを好んで食べるようなゲテモン好きなので、当然、それを頼んだ。

これはゴムか、と思わせる前歯を押し返すような噛応えに、舌にざらつくスポンジのような食感。そして後から微かに漂う独特な香り。
「また食べたいって思うもんじゃないでしょ」と聞かれ、曖昧な笑いを返した。
GWの頃は港の辺りでテントを張り釣りをする人が多いよ、と聞くに及び、それなら夕焼けの美しかったあの公園まで戻らなくても良いな、と思って、じっくりと腰を据えて呑み耽る。
途中で見掛けた書き割りのように見事な滝は昔はなかったので人工ではないかという話や、ここが通っていれば大分楽やのにというトンネル工事が長いことほったらかしであることや、そこら彼処で見掛ける土俵に舟屋の近くで練習する子供力士に地元出身の幕内の話であったり、何処の店でも隠岐誉の看板を掲げているが地元の人は好まないので何処の店でも高正宗を出しているとか、海藻焼酎「いそっ子」は磯臭過ぎてこれもまた地元の人は誰も呑まないので買うなら熟成させた「わだつみの精」がオススメだとか、安くて美味しい寿司屋に中華料理屋、後は釣りの話だとか、その他、かなりプライベートに関わる話なんかを語らったりしての2時間ほどの滞在であった。



予め用意しておいた「隠岐誉」を加えてほと良く酔いしめて漁協の隅で寝ていたのだが、未だ日も昇らぬ午前四時にイカ釣り漁船の爆音に起こされ、早々に退散するハメとなったのも今となっては良い思い出。

おでん こと
住所:島根県隠岐郡隠岐の島町港町天神原1-5 和食マップ
電話:08512-2-2397
営業時間:17:00~22:00
定休日:日曜
公式blog
cp5 mf6 re5